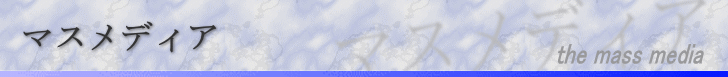第1章 お掃除プロの基本理念
「汚れ」って何?「掃除」って何?
家の密閉度が高まり、冷暖房の普及も高まるにつれ、家の中の汚れは複雑化してくる。
ゴミ、ほこり、水汚れ、油汚れ、湿気、カビ、ダニなどみんな家庭内の「汚れ」なのだ。
「汚れ」って何?どんなふうに「汚れ」がつくの? これらをよくよく解明しなくては、「汚れ」落としに挑戦はできない。
プロは理論的、科学的に考え、よく見て、工夫に工夫を重ねているものだ。
1.汚れの性質をきわめなければ、プロじゃない
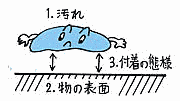 ハウスクリーニングとは、物についた汚れをとり去ることです。そこで考えなければならないことは、汚れの種類と性質です。ただやみくもにふいたりこすったりしても、効率が悪いばかりか、かえって汚れを広げてしまうこともありますので、まず、その汚れがどんな性質を持っているのかを知らなければなりません。 次に、汚れがついている物の表面の材質が問題になります。たとえ汚れが落ちても、物をきずつけてしまっては、風合いがそこなわれて、かえってきたなく感じられるようになってしまいます。そこで、汚れと接触している物の表面の材質についても考えなければならないわけです。最後に、物と汚れの付着の態様についても考えていきます。表面についているのか、しみ込んでいるのかによって、クリーニングの方法は違ってきます。このように書くと、たいへんにむずかしそうですが、家庭内の汚れはそれほど種類は多くありませんし、判断のポイントさえ覚えてしまえば、たやすくわかるようになるはずです。
ハウスクリーニングとは、物についた汚れをとり去ることです。そこで考えなければならないことは、汚れの種類と性質です。ただやみくもにふいたりこすったりしても、効率が悪いばかりか、かえって汚れを広げてしまうこともありますので、まず、その汚れがどんな性質を持っているのかを知らなければなりません。 次に、汚れがついている物の表面の材質が問題になります。たとえ汚れが落ちても、物をきずつけてしまっては、風合いがそこなわれて、かえってきたなく感じられるようになってしまいます。そこで、汚れと接触している物の表面の材質についても考えなければならないわけです。最後に、物と汚れの付着の態様についても考えていきます。表面についているのか、しみ込んでいるのかによって、クリーニングの方法は違ってきます。このように書くと、たいへんにむずかしそうですが、家庭内の汚れはそれほど種類は多くありませんし、判断のポイントさえ覚えてしまえば、たやすくわかるようになるはずです。目次へ
家の中には、いろんな汚れがある
●汚れにも種類がある
家の中の汚れにはさまざまなものがあります。棚の上のほこりや紙くず、ゴミなどのように、簡単にとり除くことができるものから、ガスレンジの煮こぼれ、レンジフードの油汚れなどすっかりこびりついてしまってなかなか落ちない汚れまで、千差万別です。また、浴室のカビも汚れの仲間といえます。
●油汚れが家の汚れの大半
一般に、汚れは水性のものと油性のものに分けられます。水性の汚れは水にとけるので、ぞうきんで水ぶきするだけでも簡単にきれいになります。しかし、家の中の汚れは多かれ少なかれ油分を含んでおり、水でふくだけでは落ちないことが多いのです。そこで、洗剤の登場になります。洗剤を加えると、水になじみにくい油分も水にとけ込んで、とり除きやすくなります。
●ぺンキの汚れはむずかしい
もう一つの分類は、染料系の汚れとそうでないものの汚れという分け方です。もともと染料というのは、ものを染めるためにあるのですから、組織の内部にしみ込んでしまい、落とすのはなかなかたいへんです。じゅうたんにペンキやインク、墨などをこぼした場合がこれにあたります。
目次へ
汚れやすい材質っていうのもある
●吸水性か耐水性かでクリーニング方法は変わる
 家の中で汚れがつかないものは全くないといってよく、ありとあらゆるものがハウスクリーニングの対象になります。表面の材質も、木、鉄、プラスチック、塗装面などさまざまです。これだけあると掃除の方法に迷ってしまうと思いますが、重要なのはその素材が水を吸い込むかどうかという点です。
家の中で汚れがつかないものは全くないといってよく、ありとあらゆるものがハウスクリーニングの対象になります。表面の材質も、木、鉄、プラスチック、塗装面などさまざまです。これだけあると掃除の方法に迷ってしまうと思いますが、重要なのはその素材が水を吸い込むかどうかという点です。●吸水性のものは、からぶき程度に
まず、吸水性の素材のクリーニングです。たとえば、布製の壁紙、ふすま、白木の柱などがあげられます。これらの物は水を吸い込みますので、原則的に水は使えません。水といっしょに水にとけた汚れまで吸い込んでしまうからです。からぶき、はたきがけなどにとどめたほうが無難でしょう。
●耐水性の物は、洗剤による変色に注意
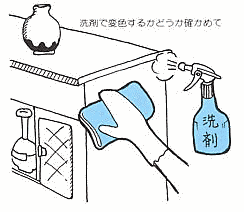 次に、耐水性の素材です。水を吸い込まない材質の物についた汚れは、ぬれぞうきんでふいたり、洗剤をつけてブラシでこすることができるので、ハウスクリーニングしやすいといえます。このとき、注意したいのは、洗剤による変色です。特にスプレーで洗剤の原液をかける場合は要注意で、洗剤がかかった部分が白く漂白されて斑になってしまうことがあります。これを防ぐためには、あらかじめ目立たない部分に洗剤の原液を塗り、濃い洗剤によって変色するかどうか確かめてから作業するとよいでしょう。変色を防ぐための方法としては、いったんぬれぞうきんで表面をふき、物の表面に水の膜を張ってからスプレーするやり方があります。こうすれば水の膜で洗剤が均一に散り、変色を起こす割合が少なくなります。
次に、耐水性の素材です。水を吸い込まない材質の物についた汚れは、ぬれぞうきんでふいたり、洗剤をつけてブラシでこすることができるので、ハウスクリーニングしやすいといえます。このとき、注意したいのは、洗剤による変色です。特にスプレーで洗剤の原液をかける場合は要注意で、洗剤がかかった部分が白く漂白されて斑になってしまうことがあります。これを防ぐためには、あらかじめ目立たない部分に洗剤の原液を塗り、濃い洗剤によって変色するかどうか確かめてから作業するとよいでしょう。変色を防ぐための方法としては、いったんぬれぞうきんで表面をふき、物の表面に水の膜を張ってからスプレーするやり方があります。こうすれば水の膜で洗剤が均一に散り、変色を起こす割合が少なくなります。●汚れた物のかたさを見きわめる
物の表面の材質を考えるとき、かたさもたいせつな条件です。せっかく汚れが落ちても物にきずがついてしまってはなんにもなりません。本来、ハウスクリーニングというのは、物をきずつけずに汚れをとるということなのですから。 表面が無限にかたければ、どんなに力を入れてこすってもきずつくことはないのですが、たとえ金属であっても、そのようにかたいものはありません。ということは、汚れよりもかたく、物よりもやわらかいものでこするというのが原則になります。
●表面加工のしてないものは、原則的にこすってもだいじょうぶ
一般の家庭で使われている建材は、木、金属、ガラス、樹脂などです。表面に何も施されていないもの、たとえば白木の柱などは、こすることに
よって表面が多少削られても、その下の材質との間に変化がないのでさほど問題はありません。ただし、木からアクが出て変色している場合は色の差が出ることがありますが、アク洗いで色抜きするか、電動サンダーで削って色をととのえればだいじょうぶです。ステンレス、窓ガラスなども表面には加工をしてありませんが、こすりすぎるとつやがなくなることもあります。これは、つやを出すために、鏡面加工が施してあるからです。
●塗装膜がはげ貰ちないように注意しながらこする
 表面が塗装や樹脂などで加工されているものの場合は、力を入れてこすることは禁物です。こすりすぎると表面の膜がはげ落ちて地肌があらわれ、周囲との風合いが全く違ってしまうからです。ただし、つや消しのペンキなどの場合は、塗装膜の厚みまではこすることができますので、新しい部分を出してきれいに見せることができます。ニスやウレタン塗装など表面につやがあるものの場合は、やはりこすりすぎに注意しましょう。光のぐあいで目立たないときにはだいじょうぶですが、そうでないとつやが全くなくなってしまうことがあります。いずれにしても、自分の目で状態を確認しながら作業を進めることが最もたいせつで、ただがむしゃらに進めると、とり返しのつかないことになりかねませんので、気をつけてください。
表面が塗装や樹脂などで加工されているものの場合は、力を入れてこすることは禁物です。こすりすぎると表面の膜がはげ落ちて地肌があらわれ、周囲との風合いが全く違ってしまうからです。ただし、つや消しのペンキなどの場合は、塗装膜の厚みまではこすることができますので、新しい部分を出してきれいに見せることができます。ニスやウレタン塗装など表面につやがあるものの場合は、やはりこすりすぎに注意しましょう。光のぐあいで目立たないときにはだいじょうぶですが、そうでないとつやが全くなくなってしまうことがあります。いずれにしても、自分の目で状態を確認しながら作業を進めることが最もたいせつで、ただがむしゃらに進めると、とり返しのつかないことになりかねませんので、気をつけてください。目次へ
汚れのつき方に注意せよ
●表面だけか、しみ込んだ汚れか
汚れというのは、基本的に物の表面につきますが、場合によっては表面についた汚れが物の内部にまでしみ込んでいくこともあります。ハウスクリーニングをきちんとするときには、この二つの汚れを分けて考えていく必要があります。
●ぶ厚い汚れはヘラでそげ落とす
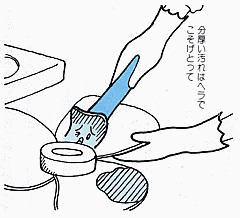 物の表面につく汚れでも、薄くつく場合と厚く盛り上がったようにつく場合とがあります。うっすらとついている場合は、こすっただけで簡単に落ちることが多いようです。一方、厚くついている場合は、少し工夫が必要です。汚れが厚いと、ただこすっただけではとれませんので、ヘラなどでこそげ落とせる場合は落としたほうが効率よく進められます。たとえば、換気扇に厚くついている油汚れは、直接洗剤を振りかけても、洗剤が油に負けてしまい、油汚れをその場で回すだけになってたいへんに効率の悪いものです。ヘラでこそげ落とす方法は、物をきずつけずにクリーニングするためにもたいへんに重要です。たとえば、スチールウールで汚れをこする場合、当然汚れの周辺もこすってしまうことになり、汚れが落ちても周辺にきずがついてしまいます。あらかじめヘラでできる限り汚れを薄くしておいてからこすれば、このようなきずあとを残すことは防げます。
物の表面につく汚れでも、薄くつく場合と厚く盛り上がったようにつく場合とがあります。うっすらとついている場合は、こすっただけで簡単に落ちることが多いようです。一方、厚くついている場合は、少し工夫が必要です。汚れが厚いと、ただこすっただけではとれませんので、ヘラなどでこそげ落とせる場合は落としたほうが効率よく進められます。たとえば、換気扇に厚くついている油汚れは、直接洗剤を振りかけても、洗剤が油に負けてしまい、油汚れをその場で回すだけになってたいへんに効率の悪いものです。ヘラでこそげ落とす方法は、物をきずつけずにクリーニングするためにもたいへんに重要です。たとえば、スチールウールで汚れをこする場合、当然汚れの周辺もこすってしまうことになり、汚れが落ちても周辺にきずがついてしまいます。あらかじめヘラでできる限り汚れを薄くしておいてからこすれば、このようなきずあとを残すことは防げます。●しみ込んだ汚れは原則的にとることはできない
部屋の模様がえをしたときなどに、タンスの形だけを残して壁紙が汚れていた……という経験はどなたにもあることと思います。これは、長い間に壁紙にしみ込んだタバコのヤニなどです。壁の絵をとりはずしたときなどは、額の形に四角の空間ができ、見苦しいものです。表面だけの汚れであれば、洗剤やぞうきんで落ちますが、もし物の内部にまでしみ込んでしまっていると、いくらこすっても落とすことはできません。きれいに落とすには、その物自体を削ってしまうしか方法がありませんが、それは、ほとんどの場合不可能です。つまり、物の内部にまでしみ込んでしまった汚れは、原則的にとることはできません。内部にしみ込んだ汚れはあきらめ、表面の汚れのうち、こすってとれる範囲をきれいにします。 物によっては漂白という方法で内部まできれいにすることができます。サッシのゴムわくのカビなどがそれです。
目次へ
水、洗剤、物理力の三要素だけが汚れ落としに必要
●「汚れを移動させる」のが掃除
汚れは消えません。清掃というのは、汚れを消してしまうのではなく、別の場所に移しかえていく作業です。そのために必要なものが、水、洗剤、物理力の三つです。たとえば、じゅうたんにソースをこぼした場合のことを考えてみましょう。ぞうきんでふいてみると、ある程度はきれいになります。でも、完全にはとれず、あとが残ってしまいます。そこで、そのソースのあとに水をかけてぬらし、こすってみます。すると、さっきよりもずっとあとが薄くなります。これはなぜでしょうか。この原理は、水がソースという汚れをとかし込み、水の移動に伴って汚れがいっしょに移動するためです。水がなければ、汚れは移動のしようがありません。水があってはじめて汚れは移動できる、つまりきれいになるというわけです。
●水、洗剤、物理力の三つで汚れを落とす
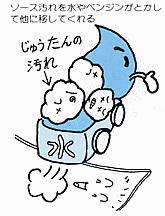 汚れを移動させるものとして、水は私たちの身近に常にあり、いつでも使えるという便利さを持っています。しかし、水溶性の汚れはとかせますが、油性の汚れはとかせません。また、表面張力が大きいので、すみなどのこまかい部分には入っていけません。この欠点を補うものが洗剤です。洗剤の役目は、主に界面活性剤の働きで表面張力を下げ、こまかい部分にまで水が入っていきやすくすることです。また、油汚れを包み込み、水に混和させることによって油汚れを運びやすくします。しかし、単に洗剤液でぬらしただけでは洗剤の作用が表面だけにとどまり、内部にまで及びません。そこで、物理力で汚れをこすりとり、その下の部分にまで洗剤を作用させる必要があります。汚れを落とすためには、汚れよりかたく、汚れがついている物よりやわらかい物でこすることが理想的です。
汚れを移動させるものとして、水は私たちの身近に常にあり、いつでも使えるという便利さを持っています。しかし、水溶性の汚れはとかせますが、油性の汚れはとかせません。また、表面張力が大きいので、すみなどのこまかい部分には入っていけません。この欠点を補うものが洗剤です。洗剤の役目は、主に界面活性剤の働きで表面張力を下げ、こまかい部分にまで水が入っていきやすくすることです。また、油汚れを包み込み、水に混和させることによって油汚れを運びやすくします。しかし、単に洗剤液でぬらしただけでは洗剤の作用が表面だけにとどまり、内部にまで及びません。そこで、物理力で汚れをこすりとり、その下の部分にまで洗剤を作用させる必要があります。汚れを落とすためには、汚れよりかたく、汚れがついている物よりやわらかい物でこすることが理想的です。目次へ
プロが素人と違うのは、「心理的な掃除法」で迫る点
●昔の掃除は道徳と結びついていた
古くから、掃除は道徳と結びつけられてきました。「上から下へ、内から外へ」と手を抜かずに行うのが主婦の務めだ、というように教え込まれてきました。時間や人手が十分にある場合はこのやり方でもよいのですが、昔でもこのような場合はまれでした。特に現代では、時間や人手が限られており、このようなやり方で全体の掃除を行うことは困難といってもよいでしょう。昔にくらべれば家具も多く、見せる収納も多いので、初めは勢いづいて上のほうから掃除を始めても、あまりの多さに下に行くまでに疲れてしまいます。それでもきれいになればよいのですが、疲れるわりにはあまりきれいにならないものです。その結果、掃除はたいへんなものだとあきらめてしまいがちです。
●光る物やすみに気をつける

全部を完璧に掃除することが不可能なら、短時間で効率よくきれいにするにはどうしたらよいかが問題になります。ここでちょっと考えたいのは、「きれいにする」ことと「きれいに見えるようにする」ことの違いです。 いくらこまごまと掃除をしても、目のいきやすい場所が汚れていれば、きれいに見えません。一方、いちばん目のいきやすいところがきれいになっていれば、気持ちよく感じるものです。そこで、まず、目のいきやすい場所を掃除することです。そして、余力があればその他の部分に広げていきます。 人間の目がいきやすいところは、光っている部分です。俗に、きれいに掃除ができている状態を「ピカピカになった」といいますが、この言葉からもわかるように、人間の目は光っている部分にたいへん敏感です。光っている場所というと、第一に思いつくのは金属部分です。たとえば、台所の蛇口や金物の部分をみがくだけでも、印象は格段に違ってきます。白い部分も光を反射しますので、光る部分と同じように考えます。戸棚の白いとびら、照明器具やその反射板など、白い部分をきれいにふき清めるように注意して、掃除を始めてみましょう。次に注意したいのは、すみの部分です。角やすみの部分にもよく目がいきます。人間は物の形を判別するときに、すみの形を見て特徴をとらえて認識するからです。ですから、いくら中央部がきれいになっていても、すみに汚れが残っていては、きれいになった感じがしません。「四角い部屋は四角く掃除する」といわれるのも、すみの掃除のたいせつさをいった言葉だと思います。
●お客さまになったつもりで部屋をながめてみる
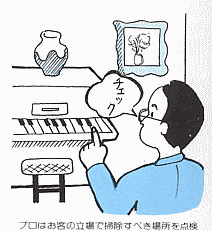 合理的な掃除の第一歩は、まず、目のいく場所から始めるということです。各家庭によって家の造作などいろいろ異なりますので、部屋を見渡して、どこに目がいきやすいか調べてみましょう。ドアの前に立ち、お客さまになったつもりで一つ一つ点検していってもよいでしょう。マンションなどの場合、まず、目につくのが部屋番号や表札の部分です。この部分は面積は小さいのですが、お客さまは必ず確認するところですから気をつけましょう。部屋が確認できたら、次にインターホンやベルを押します。ということは、ベルのボタンに目がいくということです。ボタンの上にはほこりがたまりやすいので、ここも注意して点検します。次は、ドアをあけるという動作です。ドアのノブの周辺に手あかがついているとたいへん気になるものです。さらに、家の中に一歩足を踏み入れるときには、足場を確認するために敷居の部分に目がいきます。鉄のドアの敷居がステンレスの場合は、光っているのでなおさら目がいきます。人間の目の動きをよく観察すれば、おのずから効率のよい掃除場所が浮かび上がってきます。他の場所も同じようにして、考えていけばよいのです。掃除のプロは、その家の人の背の高さから目の位置を割り出し、必ずその位置から掃除のできを確認するものです。これは、ぜひ見習ってほしいところです。古くからある清掃方法を仮に物理的清掃と呼ぶならば、このようなやり方は心理的清掃と呼べると思います。
合理的な掃除の第一歩は、まず、目のいく場所から始めるということです。各家庭によって家の造作などいろいろ異なりますので、部屋を見渡して、どこに目がいきやすいか調べてみましょう。ドアの前に立ち、お客さまになったつもりで一つ一つ点検していってもよいでしょう。マンションなどの場合、まず、目につくのが部屋番号や表札の部分です。この部分は面積は小さいのですが、お客さまは必ず確認するところですから気をつけましょう。部屋が確認できたら、次にインターホンやベルを押します。ということは、ベルのボタンに目がいくということです。ボタンの上にはほこりがたまりやすいので、ここも注意して点検します。次は、ドアをあけるという動作です。ドアのノブの周辺に手あかがついているとたいへん気になるものです。さらに、家の中に一歩足を踏み入れるときには、足場を確認するために敷居の部分に目がいきます。鉄のドアの敷居がステンレスの場合は、光っているのでなおさら目がいきます。人間の目の動きをよく観察すれば、おのずから効率のよい掃除場所が浮かび上がってきます。他の場所も同じようにして、考えていけばよいのです。掃除のプロは、その家の人の背の高さから目の位置を割り出し、必ずその位置から掃除のできを確認するものです。これは、ぜひ見習ってほしいところです。古くからある清掃方法を仮に物理的清掃と呼ぶならば、このようなやり方は心理的清掃と呼べると思います。目次へ
2、プロが常時持ち歩く「洗剤、清掃薬剤、器具」
●知らないで使うから洗剤使用ミスが起こる
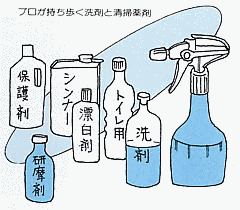 掃除に使われる洗剤にはいろいろな種類があります。洗剤、洗浄剤、溶剤、研磨剤などがそれで、機能を高めるために多くは組み合わせて製品化されています。 これらの洗剤を使う目的は、短時間に効率を上げ、労力を省くことにあります。もし、まちがった使い方をすれば、効率が悪くなるだけではなく、きずをつけたり、変色させたりという結果になりかねません。まず、一つ一つの洗剤や薬剤の性質や効力を知ることです。これは、よりいっそう効果を上げるための基本といえます。
掃除に使われる洗剤にはいろいろな種類があります。洗剤、洗浄剤、溶剤、研磨剤などがそれで、機能を高めるために多くは組み合わせて製品化されています。 これらの洗剤を使う目的は、短時間に効率を上げ、労力を省くことにあります。もし、まちがった使い方をすれば、効率が悪くなるだけではなく、きずをつけたり、変色させたりという結果になりかねません。まず、一つ一つの洗剤や薬剤の性質や効力を知ることです。これは、よりいっそう効果を上げるための基本といえます。●洗剤は、水と油を仲よくさせるもの
洗剤というのは、主に界面活性剤の働きで汚れを落とすものです。ふだん私たちが使っている洗剤は、この界面活性剤を主剤に、使用効果を高めるための助剤(ビルダー)を加えたもので、合成洗剤と呼ばれています。掃除に使う代表的な洗剤には、住宅用洗剤、住宅用強力洗剤があります。
●洗浄剤は、酸性とアルカリ性を混用しないように
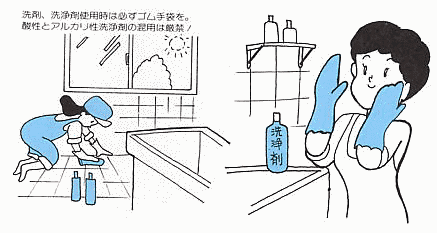 洗浄剤というのは、酸やアルカリの化学作用によって汚れを落とすものです。トイレ用の洗浄剤(酸性)、漂白剤(アルカリ性)などがあります。洗浄剤は、洗剤にくらべて作用が強いので、肌に直接つけると炎症などを起こすことがあります。扱うときは必ずゴム手袋をはめ、こぼしたり飛ばしたりしないように十分に注意しましょう。また、幼児がふれる危険性のない場所に保管しておきます。酸性タイプの洗浄剤の代表は、トイレタイル用洗剤として市販されているものです。主成分は塩酸で、タンパク質や有機物を分解する力を利用して汚れを落としていきます。市販されている洗浄剤は、この塩酸を薄め、界面活性剤などを調合してあり、便器についた汚れ、水あか、尿石などを溶解し、タイルや目地の黒ずみをきれいにします。一方のアルカリタイプの洗浄剤は、次亜鉛素酸ナトリウムを主成分にし、漂白と殺菌の二つの作用があります。通常、漂白剤(塩素系)、カビ取り剤として市販されており、黒ずみを漂白し、カビを殺菌して発生を抑えます。洗浄剤を使うときに注意したいことは、酸性のものとアルカリ性のものをいっしょに使わないことです。この二つのタイプのものをいっしょに使うと、急激に分解反応が起こり、塩素ガスが発生します。発生したガスを大量に吸い込むと、気管の粘膜を傷つけて浮腫ができ、呼吸困難などを引き起こします。その毒性はすさまじいもので、第一次世界大戦では毒ガスとして使用されたくらいです。このような危険性があるのですから、絶対に混用してはなりません。特に注意しなければならないことは、トイレ用の洗浄剤の中にはこの双方のタイプがあり、作業中に一方のタイプがなくなったので、新しく買った他方のタイプを使い足した場合も混合したことになってしまうことです。混合によるガス発生の危険はこれらの洗浄剤のほかにもありえますので、作業中はドアや窓を大きくあけて十分に換気するようにします。もし、作業中に塩素臭が強くしたり気分が悪くなった場合は、すぐその場を離れてそれ以上ガスを吸わないようにします。塩素ガスによる事故は全国で多数発生しており、これが原因で亡くなった方もいます。けっして楽観せず、体に少しでも変調を感じたときはすぐに医者に相談してください。
洗浄剤というのは、酸やアルカリの化学作用によって汚れを落とすものです。トイレ用の洗浄剤(酸性)、漂白剤(アルカリ性)などがあります。洗浄剤は、洗剤にくらべて作用が強いので、肌に直接つけると炎症などを起こすことがあります。扱うときは必ずゴム手袋をはめ、こぼしたり飛ばしたりしないように十分に注意しましょう。また、幼児がふれる危険性のない場所に保管しておきます。酸性タイプの洗浄剤の代表は、トイレタイル用洗剤として市販されているものです。主成分は塩酸で、タンパク質や有機物を分解する力を利用して汚れを落としていきます。市販されている洗浄剤は、この塩酸を薄め、界面活性剤などを調合してあり、便器についた汚れ、水あか、尿石などを溶解し、タイルや目地の黒ずみをきれいにします。一方のアルカリタイプの洗浄剤は、次亜鉛素酸ナトリウムを主成分にし、漂白と殺菌の二つの作用があります。通常、漂白剤(塩素系)、カビ取り剤として市販されており、黒ずみを漂白し、カビを殺菌して発生を抑えます。洗浄剤を使うときに注意したいことは、酸性のものとアルカリ性のものをいっしょに使わないことです。この二つのタイプのものをいっしょに使うと、急激に分解反応が起こり、塩素ガスが発生します。発生したガスを大量に吸い込むと、気管の粘膜を傷つけて浮腫ができ、呼吸困難などを引き起こします。その毒性はすさまじいもので、第一次世界大戦では毒ガスとして使用されたくらいです。このような危険性があるのですから、絶対に混用してはなりません。特に注意しなければならないことは、トイレ用の洗浄剤の中にはこの双方のタイプがあり、作業中に一方のタイプがなくなったので、新しく買った他方のタイプを使い足した場合も混合したことになってしまうことです。混合によるガス発生の危険はこれらの洗浄剤のほかにもありえますので、作業中はドアや窓を大きくあけて十分に換気するようにします。もし、作業中に塩素臭が強くしたり気分が悪くなった場合は、すぐその場を離れてそれ以上ガスを吸わないようにします。塩素ガスによる事故は全国で多数発生しており、これが原因で亡くなった方もいます。けっして楽観せず、体に少しでも変調を感じたときはすぐに医者に相談してください。●塗料を落とすにはベンジンやシンナーを
 溶剤にはベンジン、塗料用のシンナー、ラッカーシンナーなどがあり、ペンキやニスなどの塗料をふきとるために使われます。これらは、洗剤や洗浄剤ではとることができません。これらの塗料は、ついた時点ですぐとることがいちばんよく、乾いてしまっては溶解させるのに手間がかかります。塗料には種類が多く、染料をとかしている溶剤も種類が多いので、家庭では、それに見合った溶剤を見分けることは困難です。プロであれば、ある程度見分けて溶剤も的確に選ぶことができますが、家庭では、目立たないところで試しながらやるのがよいでしょう。家庭で手に入りやすいのは、ラッカーシンナー、塗料用シンナー、ベンジンなどです。ここで重要なのは、ラッカーシンナー(ラッカー薄め液、第一石油類)と塗料用シンナー(ペイント薄め液、第二石油類)との違いです。ラッカーをとかすものがラッカーシンナーで、いわゆるシンナーくさいのが特徴です。一方、油性ペンキをとかすものが塗料用シンナーで、どちらかといえば石油くさいにおいがします。ラッカーシンナーは塗料用シンナーにくらべて発火点が低くて溶解力が高く、ペンキ汚れなどを落とす力が強い反面、プラスチックなどはとかしてしまうので注意が必要です。そこで、まず塗料用シンナーを使い、それで落ちないときはラッカーシンナーを使うようにしたほうが無難です。最後にベンジンは、服についた口紅などをとるのに用いられますが、その他、じゆうたんについた油汚れにも有効です。
溶剤にはベンジン、塗料用のシンナー、ラッカーシンナーなどがあり、ペンキやニスなどの塗料をふきとるために使われます。これらは、洗剤や洗浄剤ではとることができません。これらの塗料は、ついた時点ですぐとることがいちばんよく、乾いてしまっては溶解させるのに手間がかかります。塗料には種類が多く、染料をとかしている溶剤も種類が多いので、家庭では、それに見合った溶剤を見分けることは困難です。プロであれば、ある程度見分けて溶剤も的確に選ぶことができますが、家庭では、目立たないところで試しながらやるのがよいでしょう。家庭で手に入りやすいのは、ラッカーシンナー、塗料用シンナー、ベンジンなどです。ここで重要なのは、ラッカーシンナー(ラッカー薄め液、第一石油類)と塗料用シンナー(ペイント薄め液、第二石油類)との違いです。ラッカーをとかすものがラッカーシンナーで、いわゆるシンナーくさいのが特徴です。一方、油性ペンキをとかすものが塗料用シンナーで、どちらかといえば石油くさいにおいがします。ラッカーシンナーは塗料用シンナーにくらべて発火点が低くて溶解力が高く、ペンキ汚れなどを落とす力が強い反面、プラスチックなどはとかしてしまうので注意が必要です。そこで、まず塗料用シンナーを使い、それで落ちないときはラッカーシンナーを使うようにしたほうが無難です。最後にベンジンは、服についた口紅などをとるのに用いられますが、その他、じゆうたんについた油汚れにも有効です。●研摩剤は物をきずつけないようにすることが肝心
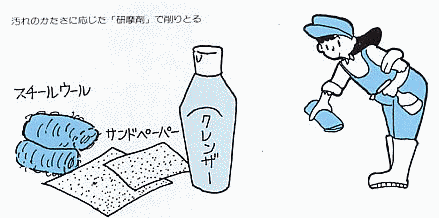 汚れが物にしつこくついている場合は、ぞうきんでふいてもなかなか落ちないので、削り落としてきれいにするしかありません。そのために使われるのが、研摩剤です。研摩剤には、みがき砂、クレンザー、サンドペーパー、スチールウールなどの種類があります。みがき砂は昔からあるもので、天然右をこまかく砕いて精錬し、粒をととのえたものです。このみがき砂に洗剤などを配合すると、クレンザーになります。初期のクレンザーは紙箱入りのタイプで粒子もあらかったのですが、その後、研摩剤の粒子がこまかくなり、現在ではクリームクレンザーなどの液状のものが主流になっています。これは、かまどからガス台へと生活様式が変化し、みがく対象が変わってきたからです。サンドペーパーは、みがき砂を紙の上に均一にのばして接着したものです。研摩剤のあらさによって番号がつけられており、これを番手といいます。番号が大きくなるにつれて、粒子がこまかくなります。みがくものの材質によって番手を選びます。スチールウールは、鉄をきわめて細い糸状に伸ばして丸めたものです。洗剤をつけたものもあります。このスチールウールは金たわしとは違います。研摩剤というのは、汚れを削り落とすために使うのですから、あらければあらいほど落とす力は強いのですが、一方、汚れがついている物まで削ってきずをつけてしまうという欠点があります。ということは、汚れよりかたくて、汚れがついている物よりやわらかいものがいちばんよいということになります。しかし、汚れのかたさや汚れのついている物のかたさはいろいろですから、一つの研摩剤ですべての物に使えるとは限りません。まず、汚れのついている物のかたさを調べ、いちばんふさわしい研摩剤を使うことがたいせつです。汚れを落とすことに気をとられるあまり、やみくもにこすってきずをつけることがないよう、きずがつくかどうか目で確かめながら行うようにしてください。もし、きずがつくようなら、汚れが多少残ってもそこでとめるしかありません。
汚れが物にしつこくついている場合は、ぞうきんでふいてもなかなか落ちないので、削り落としてきれいにするしかありません。そのために使われるのが、研摩剤です。研摩剤には、みがき砂、クレンザー、サンドペーパー、スチールウールなどの種類があります。みがき砂は昔からあるもので、天然右をこまかく砕いて精錬し、粒をととのえたものです。このみがき砂に洗剤などを配合すると、クレンザーになります。初期のクレンザーは紙箱入りのタイプで粒子もあらかったのですが、その後、研摩剤の粒子がこまかくなり、現在ではクリームクレンザーなどの液状のものが主流になっています。これは、かまどからガス台へと生活様式が変化し、みがく対象が変わってきたからです。サンドペーパーは、みがき砂を紙の上に均一にのばして接着したものです。研摩剤のあらさによって番号がつけられており、これを番手といいます。番号が大きくなるにつれて、粒子がこまかくなります。みがくものの材質によって番手を選びます。スチールウールは、鉄をきわめて細い糸状に伸ばして丸めたものです。洗剤をつけたものもあります。このスチールウールは金たわしとは違います。研摩剤というのは、汚れを削り落とすために使うのですから、あらければあらいほど落とす力は強いのですが、一方、汚れがついている物まで削ってきずをつけてしまうという欠点があります。ということは、汚れよりかたくて、汚れがついている物よりやわらかいものがいちばんよいということになります。しかし、汚れのかたさや汚れのついている物のかたさはいろいろですから、一つの研摩剤ですべての物に使えるとは限りません。まず、汚れのついている物のかたさを調べ、いちばんふさわしい研摩剤を使うことがたいせつです。汚れを落とすことに気をとられるあまり、やみくもにこすってきずをつけることがないよう、きずがつくかどうか目で確かめながら行うようにしてください。もし、きずがつくようなら、汚れが多少残ってもそこでとめるしかありません。●掃除の仕上げに便利な保護剤
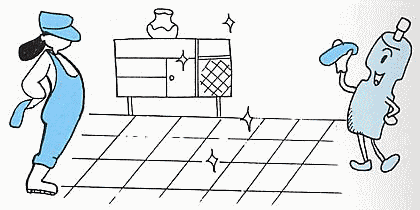 掃除の仕上げに使うと便利なものに保護剤があります。これは、掃除をした面に塗りつけることによって材質を保護したり、つやを出したり、汚れをつきにくくさせるためのものです。仕上げ剤とも呼ばれています。床に塗るワックス、家具などに塗るシリコン系のもの、シリコンをまぜたガラス用洗剤などが保護剤です。つやが出ると物がとてもきれいに見えるようになり、清掃効果をよりいっそう高く見せる方法としては便利なものです。また、美観だけではなく、これらの保護剤にはその名のとおり保護作用もあります。たとえば、床にワックスを塗っておけば、足でこすられることによってきずがつくのを防ぐことができます。これは、ワックスの層ができるためです。床ワックスというと、以前は水ロウ系のものしかなくて、たいへんに滑りやすかったのですが、最近では樹脂ワックスが多いので、この欠点は改善されています。樹脂ワックスは床にマニキュアを塗ったような一種の塗装面を作り、美しいつやを出します。しかし、この樹脂ワックスの上にシリコン入りのガラス用洗剤をこぼしたり、落としたりしないことです。とたんに滑りやすくなります。樹脂ワックスは、床の保護つや出しばかりでなく、簡易塗装にも利用できます。家具の光沢が薄れたときなどに全面に塗ると美しいつやがよみがえります。また、ニスを塗った家具の一部にきずがついたときにも樹脂ワックスは便利で、その部分にだけ樹脂ワックスを塗ると、きずを目立たなくすることができます。ワックスを塗ることによって、きずの表面をなめらかにし、乱反射を抑えてきずを目立たなくするわけです。このように、保護剤にはたくさんの利点がありますが、欠点もあります。欠点は、長い間には、保護剤自体が変質したり、変色してしまうことです。本来からいえば、清掃後の物には何もつけないのがいちばんよいといえるかもしれません。しかし、使う場合は欠点もきちんと理解し、耐久性を考えて、時期がきたらこれらの保護膜を洗剤などできれいに剥離し(剥離法は54ページ参照)、新たに保護剤を使うようにするとよいと思います。
掃除の仕上げに使うと便利なものに保護剤があります。これは、掃除をした面に塗りつけることによって材質を保護したり、つやを出したり、汚れをつきにくくさせるためのものです。仕上げ剤とも呼ばれています。床に塗るワックス、家具などに塗るシリコン系のもの、シリコンをまぜたガラス用洗剤などが保護剤です。つやが出ると物がとてもきれいに見えるようになり、清掃効果をよりいっそう高く見せる方法としては便利なものです。また、美観だけではなく、これらの保護剤にはその名のとおり保護作用もあります。たとえば、床にワックスを塗っておけば、足でこすられることによってきずがつくのを防ぐことができます。これは、ワックスの層ができるためです。床ワックスというと、以前は水ロウ系のものしかなくて、たいへんに滑りやすかったのですが、最近では樹脂ワックスが多いので、この欠点は改善されています。樹脂ワックスは床にマニキュアを塗ったような一種の塗装面を作り、美しいつやを出します。しかし、この樹脂ワックスの上にシリコン入りのガラス用洗剤をこぼしたり、落としたりしないことです。とたんに滑りやすくなります。樹脂ワックスは、床の保護つや出しばかりでなく、簡易塗装にも利用できます。家具の光沢が薄れたときなどに全面に塗ると美しいつやがよみがえります。また、ニスを塗った家具の一部にきずがついたときにも樹脂ワックスは便利で、その部分にだけ樹脂ワックスを塗ると、きずを目立たなくすることができます。ワックスを塗ることによって、きずの表面をなめらかにし、乱反射を抑えてきずを目立たなくするわけです。このように、保護剤にはたくさんの利点がありますが、欠点もあります。欠点は、長い間には、保護剤自体が変質したり、変色してしまうことです。本来からいえば、清掃後の物には何もつけないのがいちばんよいといえるかもしれません。しかし、使う場合は欠点もきちんと理解し、耐久性を考えて、時期がきたらこれらの保護膜を洗剤などできれいに剥離し(剥離法は54ページ参照)、新たに保護剤を使うようにするとよいと思います。目次へ
| 界面活性剤とは |
 界面というのは、物と物の境界という意味です。液体と空気との境界面、すなわち表面であったり、液体と液体、たとえば水と油の境目であったり…これらはすべて界面です。このように性質の異なる物どうしの境界面には、その物には本来ない特別の性質があらわれます。その主なものが表面張力です。たとえば、水と空気の境界面にもこの表面張力が働き、アメンボウが浮かんだり、草の上で露が丸くなったりするわけです。界面活性剤というのは、この表面張力をとり除くための物質です。たとえていえば、異なる物質どうしを結びつける仲人のような役割をしているわけです。親油性つまり油脂分になじむ分子と、親水性つまり水になじむ分子が一体になっており、水と油という相反する性質を兼ね備えていることになります。ですから、本来まざり合うことのない水と油が、界面活性剤を使うことによってまざり合うことができるのです。表面張力がなくなると、水は物のすみのほうまで入り込んで、汚れを運び出すことができます。また、一度包み込んだ汚れを再び物に付着させない作用もありますから、洗い流したりふきとったりすることが容易になり、掃除の効率はぐっとよくなります。 界面というのは、物と物の境界という意味です。液体と空気との境界面、すなわち表面であったり、液体と液体、たとえば水と油の境目であったり…これらはすべて界面です。このように性質の異なる物どうしの境界面には、その物には本来ない特別の性質があらわれます。その主なものが表面張力です。たとえば、水と空気の境界面にもこの表面張力が働き、アメンボウが浮かんだり、草の上で露が丸くなったりするわけです。界面活性剤というのは、この表面張力をとり除くための物質です。たとえていえば、異なる物質どうしを結びつける仲人のような役割をしているわけです。親油性つまり油脂分になじむ分子と、親水性つまり水になじむ分子が一体になっており、水と油という相反する性質を兼ね備えていることになります。ですから、本来まざり合うことのない水と油が、界面活性剤を使うことによってまざり合うことができるのです。表面張力がなくなると、水は物のすみのほうまで入り込んで、汚れを運び出すことができます。また、一度包み込んだ汚れを再び物に付着させない作用もありますから、洗い流したりふきとったりすることが容易になり、掃除の効率はぐっとよくなります。 |
3、奥さんたちはほんとの「掃き掃除」をしていない
お宅に「ほうき」が何本ある?畳を正しく掃けますか?
●ほうきは必要に応じて用意しよう
現在では電気掃除機が普及してきて、どこの家庭にも必ず一台はあり、掃除するときに、ほうきを使うことは少なくなってきました。しかし、ほうきは使いようによっては意外と役立つことも多く、手軽に使えるのも利点の一つです。
●ほうきの種類
どの家庭にも一本はあるほうきを見直してみましょう。
座敷ぼうき
ほうききびの穂で作られたもので、和室の座敷を掃くのに使われたため、こう呼ばれています。
シユロぼうき
かつては、゛京ぼうき″などとも呼ばれ、関西地方で好まれた座敷ぼうきの一つです。先がやわらかで、こまかいゴミもよくとれるので、プラスチックタイルなどの化学床材にも適し、玄関、ベランダなどの外回りにも一本用意しておくと便利です。
シダぼうき
シダの繊維を使ったもので、庭の落ち葉などあらいゴミを掃くのに適しています。
自在ぽうき
毛足の短い毛が横一列に植えられており、首が自由に動くので家具のすき間や階段を掃くときに便利です。どちらかというと業務用でビルの清掃など広い場所の清掃向きです。
化学モップ
モップに薄く油をつけて、ほこりを吸着しやすくしたものです。
竹ぼうき
外回りの掃除に使います。庭が広ければ、什製のくま手が便利です。
荒神ぼうき
“荒神”というのは、かまどの神様のことで、昔は台所に祭られていました。このほうきは、台所を掃除するのに使ったことから、名づけられました。机の上の清掃、ソファやカーテンのほこり取り、押入れのすみのゴミなど、ちょっとしたゴミをとるのに向きます。トイレ用にも一つ用意しておくと便利です。
ささらぼうき
じゆうたんのゴミやほこりをとったり、汚れをかき出すときに使います。
ちり取り
使いがってのよいものを、室内用、外回り用とそろえておきましょう。
●前に進みながら掃くとカラスの足あと
 ほうきを使うときは、原則として後ろに下がりながら行います。この動作はほうきに限らず、電気掃除機やモップを使用する場合も同じです。これは、きれいに掃除した床に汚れの足あとをつけないためで、特に、じゆうたんに掃除機をかけたり、モップで床にワックスをかけたりする場合には、前に進みながら行うと足あとがついて目立ってしまいます。
ほうきを使うときは、原則として後ろに下がりながら行います。この動作はほうきに限らず、電気掃除機やモップを使用する場合も同じです。これは、きれいに掃除した床に汚れの足あとをつけないためで、特に、じゆうたんに掃除機をかけたり、モップで床にワックスをかけたりする場合には、前に進みながら行うと足あとがついて目立ってしまいます。
●ニ種類の掃き方を使い分けてればプロ級
はじき掃き 座敷ぼうきやシダぼうきを使い、ゴミをはじくようにして集めます。畳のほか、玄関や庭のれんがやタイルのように表面がデコボコしてゴミがとりにくい場所に使いますが、ほこりを舞い上げてしまうという難点もあります。押さえ掃き 自在ぼうきを使って、床をするように掃きます。プラスチックタイル、クッションフロア、大理石のように、床の表面が比較的なめらかな場所で行います。ほこりも舞い上がりにくく、効率のよい作業ができます。
目次へ
プロ流の「電気掃除機」テクニックを秘密でご伝授しよう
●電機掃除機の利点
電機掃除機は、ゴミを吸い込んでゴミフィルターにとりますので、ほうきのようにほこりを舞い上げることの少ないのが特徴です。ゴミを吸い込むということは、空気の流れにゴミをのせて移動させることです。これは水を使って掃除するときに、汚れを流水にのせて移動させるのと同じ原理です。現在出回っている電気掃除機は、ゴミをためる部分が紙フィルターになっているものが主流で、吸い込んだゴミの処分が楽にできるようになっています。また、近年特に、ダニによるアレルギー疾患がふえており、健康を脅かすダニの存在が大きくクローズアップされています。ダニを集めて熱で殺すという、ダニ除去効果の高い電気掃除機が売り出されているのも、こういった事情があるのでしょう。
●電機掃除機にはこんなものもある
[アップライト型]
吸い込み口のブラシが回転して、じゅうたんの毛足に埋もれたほこりをたたくと同時にかき出し、フィルター・パックに吸い込みます。じゅうたんの上を土足で歩く習慣が定着している海外では、このタイプが主流です。
[乾湿両様型]
通常の竃気掃除機は、うっかり水を吸い込むと故障したり、漏電の原因となったりして危険です。しかしこのタイブの電気掃除機なら乾いたゴミはもちろんぬれたゴミや汚水まで吸い込んでくれます。本体が大きめで、小石なども吸い込み、屋外での利用に便利です。
[エクストラクター]
水を吹きかけると同時に吸い込む機構になっています。業務用では、じゅうたんのクリーニングなどによく用いられます。
[ダニ退治用 温風タイプ]
ダニのウイークポイントは乾燥と熱。50度以上になるとほとんどのダニが死滅します。この温風タイプの挿除機は、モーターの排気熟を利用した「温風循環式」のもので、ホースや紙フィルター内の温度を50度以上に上げ、吸いとったゴミとともにダニを殺します。
●あると便利なその他の掃除機
 このほか、粘着テープにゴミ、髪の毛などを吸着させるローラー式の掃除機や、床に落ちた食べくずや髪の毛などをとるときに便利な手動式掃除機もあります。これらは、フローリングやプラスチックタイルの床だけでなく、じゅうたん、畳にも簡単に使えます。特に、キッチンでうっかりグラスを割ったときなど、粘着ローラー式掃除機を使うと、小さな破片を吸着してとり除けます。ただし、水にぬれたものは粘着テープにつきません。
このほか、粘着テープにゴミ、髪の毛などを吸着させるローラー式の掃除機や、床に落ちた食べくずや髪の毛などをとるときに便利な手動式掃除機もあります。これらは、フローリングやプラスチックタイルの床だけでなく、じゅうたん、畳にも簡単に使えます。特に、キッチンでうっかりグラスを割ったときなど、粘着ローラー式掃除機を使うと、小さな破片を吸着してとり除けます。ただし、水にぬれたものは粘着テープにつきません。
●プロは、吸い口を床に密着させる
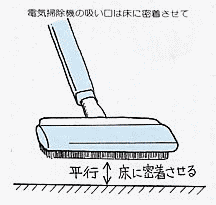 電気掃除機の使い方”というとあたりまえのようですが、じょうずに使いこなすかそうでないかで、掃除の効率や仕上がりのよさが違ってきます。まずたいせつなことは、電気掃除機の吸い口(ブラシ)が、床面と平行になるようにパイプ柄を持つことです。つまり、ブラシを床に密着させるわけです。簡単なようですが、案外このことにむとんちやくに掃除機を動かし、吸い込み口と床の間にすき間ができて効率が落ちていることに気づかずにいることが多いようです。
電気掃除機の使い方”というとあたりまえのようですが、じょうずに使いこなすかそうでないかで、掃除の効率や仕上がりのよさが違ってきます。まずたいせつなことは、電気掃除機の吸い口(ブラシ)が、床面と平行になるようにパイプ柄を持つことです。つまり、ブラシを床に密着させるわけです。簡単なようですが、案外このことにむとんちやくに掃除機を動かし、吸い込み口と床の間にすき間ができて効率が落ちていることに気づかずにいることが多いようです。
●プロは、掃除機の本体を片手に持って作業する
 プロの場合は、掃除機の本体を片手に持ち、もう一方の手でパイプ柄を使います。これは床に本体をおくと小回りのきく作業がしにくいことと、本体を無理に引っばってしまい、床をきずつけてしまうことがあるからです。
プロの場合は、掃除機の本体を片手に持ち、もう一方の手でパイプ柄を使います。これは床に本体をおくと小回りのきく作業がしにくいことと、本体を無理に引っばってしまい、床をきずつけてしまうことがあるからです。
●プロがじゅぅたんに電機掃除機をかけるとき
 じゅうたん電機掃除機をかけるコツは、まずジグザグに掃除してゴミやほこりを吸いとってから、吸い込み口でじゅうたんの毛足の方向をそろえて仕上げることです。また、きれいに毛足をそろえたじゅうたんに足あとが残らないように、部屋の奥(窓側)のほうから入り口に向かって後ろ向きに進むことも、プロなら心がけます。
じゅうたん電機掃除機をかけるコツは、まずジグザグに掃除してゴミやほこりを吸いとってから、吸い込み口でじゅうたんの毛足の方向をそろえて仕上げることです。また、きれいに毛足をそろえたじゅうたんに足あとが残らないように、部屋の奥(窓側)のほうから入り口に向かって後ろ向きに進むことも、プロなら心がけます。
●ふき掃除をスムーズにするための準備
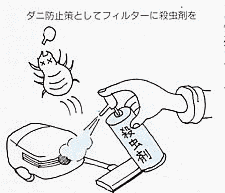 ふき掃除をする前に、どんな場所でもあらかじめ電気掃除機をかけておけば、ゴミやほこりが少なくなり、ふき掃除の作業がはかどります。また、汚れやほこりが多い場所で電気掃除機を使ったあとは、吸い込み口やブラシ部分をよく洗剤ぶきしてから、ほかの場所に移すようにします。ブラシがきたないまま使うと、汚れのあとをつけてしまうことがありますので、気をつけましょう。昨今問題となっているダニ退治は、こまめに電気掃除機で吸いとることが第一のポイントです。さらに、掃除機を使い終わってゴミを捨てたら、フィルターに殺虫剤を少しかけておくとダニの驚殖が予防できます。
ふき掃除をする前に、どんな場所でもあらかじめ電気掃除機をかけておけば、ゴミやほこりが少なくなり、ふき掃除の作業がはかどります。また、汚れやほこりが多い場所で電気掃除機を使ったあとは、吸い込み口やブラシ部分をよく洗剤ぶきしてから、ほかの場所に移すようにします。ブラシがきたないまま使うと、汚れのあとをつけてしまうことがありますので、気をつけましょう。昨今問題となっているダニ退治は、こまめに電気掃除機で吸いとることが第一のポイントです。さらに、掃除機を使い終わってゴミを捨てたら、フィルターに殺虫剤を少しかけておくとダニの驚殖が予防できます。
●先の細いノズルを使い、狭い場所の掃除を
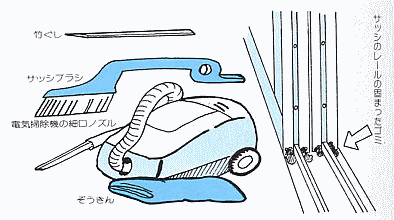 電気掃除機の付属部品を有効に使うと、掃除も効率よく進みます。先の細くなったノズルをセットすると吸い込む力も強く、ふつうの床用は入らない狭い場所や、壁際のすみなどのほこりやゴミをきれいに吸いとってくれます。
電気掃除機の付属部品を有効に使うと、掃除も効率よく進みます。先の細くなったノズルをセットすると吸い込む力も強く、ふつうの床用は入らない狭い場所や、壁際のすみなどのほこりやゴミをきれいに吸いとってくれます。
●サッシのレールのすみに固まったゴミのとり方
アルミサッシのレールは複雑な形をしていて、なかなか掃除しにくいところです。ことにすみの部分は、ゴミやほこり、髪の毛などがたまりやすいうえによく目立ち、とり除きにくいもの。そこでまず、ブラシや竹ぐしなどを使って、固まったゴミをすみからはがすようにしてゆるめ、次に電気掃除機の先の細くなったノズルでおおまかにゴミを吸い込み、最後にかたくしぼったぞうきんの角の部分を使ってふきとります。つまり、段階を追ってだんだんゴミの量を減らしていくわけです。
●戸棚、本棚のゴミのとり方
棚はぞうきんでふくのがふつうですが、ほこりをすみのほうに押し込めてしまってうまくとれないということがよくあります。すみの汚れというのはけっこう目立つものですし、食器棚ならほうったままにしているとたいへん不潔です。ふきんやぞうきんでふく前に、先の細いノズルをつけた電気掃除機で吸いとっておきます。場合によってはそれだけでぞうきんがけの必要もないくらいきれいになります。
●障子の桟のほこりのとり方
障子の桟にうっすらとほこりがたまっているのは見苦しいものです。単にほこりが桟の上にのっているだけですから、掃除は簡単。電気掃除機で吸えばすぐとれます。ぞうきんでふくと障子紙が破れたり、桟の汚れがかえって広がってしまうこともありますので注意しましょう。
●玄関のタイルのゴミも電気掃除機で
タイルは目地の部分との段差があり、ほうきで掃くと目地に砂やゴミが残り、ちり取りでとろうとしてもなかなかうまくいかないものです。こういう部分には電気掃除機を使うと一気に吸いとってくれます。
目次へ
4、プロ級「ふき掃除」は、ぞうきんテクニックにあるといっていい
ぞうきんテクニック五パターン公開
●プロの掃除具“三種の神器”
ハウスクリーニングというのは汚れを消し去ることではなく、別の場所へと移しかえることです。移動させるためには物についている汚れをこすり、浮かさなくてはなりません。このように、汚れをこすりとり、別の場所に移しかえるために使うのが用具です。そのかたさにより、三段階に分けました。まず、初めにぞうきんでふいてみて、落ちない場合はブラシを使い、それでも落ちないときにはスチールウールを使っていきます。やわらかいものから段階的に使っていけば、物にきずをつけることなくきれいにすることができます。
●プロのぞうきんは古タオルそのまんま
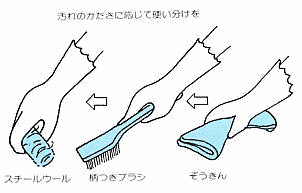 ハウスクリーニングでいちばん使われるのがぞうきんです。あまりにあたりまえすぎるようですが、実はこれに多くのポイントが含まれているのです。まず、形です。ふつうは古タオルなどを三つ折りないしは四つ折りにしてぬい合わせて使っていますが、プロはぬわずに使います。これには二つの利点があります。一つは、折りたたみ直すことによってたくさんの面が使え、洗う回数が少なくてすむことです。洗うときも、伸ばして洗えば汚れも落ちやすくなります。プロはこれを次から次へととりかえて使うので、たくさん持参します。もう一つの利点は、物に合わせて形を変えられることです。小さくすみに押し込んで使うこともできれば、伸ばしてくつみがきのように使うこともできます。ぬい合わせたぞうきんには、こういう芸当はできません。
ハウスクリーニングでいちばん使われるのがぞうきんです。あまりにあたりまえすぎるようですが、実はこれに多くのポイントが含まれているのです。まず、形です。ふつうは古タオルなどを三つ折りないしは四つ折りにしてぬい合わせて使っていますが、プロはぬわずに使います。これには二つの利点があります。一つは、折りたたみ直すことによってたくさんの面が使え、洗う回数が少なくてすむことです。洗うときも、伸ばして洗えば汚れも落ちやすくなります。プロはこれを次から次へととりかえて使うので、たくさん持参します。もう一つの利点は、物に合わせて形を変えられることです。小さくすみに押し込んで使うこともできれば、伸ばしてくつみがきのように使うこともできます。ぬい合わせたぞうきんには、こういう芸当はできません。
●たかがぞうきん、されどぞうきん
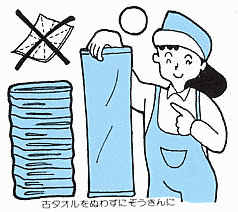 一口にぞうきんといっても、いろいろなふき方があり、ざっとあげただけでも、洗剤ぶき、水ぶき、からぶき、脱水ぶき、吸いとりぶきなどさまざまな種類があります。ふき方を誤ると、効率が悪くて汚れが落ちないばかりでなく、場合によっては物をきずつけてしまうこともあります。たかがぞうきん、と思いがちですが、ぞうきん一枚で驚くほどきれいにすることもできるのですから、正しい使い方を知り、意識的に使い分けるようにしてください。
一口にぞうきんといっても、いろいろなふき方があり、ざっとあげただけでも、洗剤ぶき、水ぶき、からぶき、脱水ぶき、吸いとりぶきなどさまざまな種類があります。ふき方を誤ると、効率が悪くて汚れが落ちないばかりでなく、場合によっては物をきずつけてしまうこともあります。たかがぞうきん、と思いがちですが、ぞうきん一枚で驚くほどきれいにすることもできるのですから、正しい使い方を知り、意識的に使い分けるようにしてください。
●プロは、洗剤をぬれぞうきんにスプレーする!
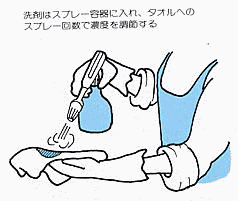 まず、洗剤ぶきです。これは汚れをとる方法として最も多く使われるものです。一般的には、洗剤をバケツの中にとかし、この中でぞうきんをしぼって使いますが、この方法では洗剤濃度が一定で、汚れぐあいに合わせることができません。それに、バケツの洗剤液がすぐに汚れてしまい、きたない水でふくことに抵抗を感じることもあります。かといって、何回もバケツの洗剤液を作り直していたのでは、不経済です。プロは、この方法をとらず、しぼったぬれぞうきんに洗剤をスプレーして使います。スプレーすることによって洗剤が均一に散り、バケツに洗剤をとかしたのと同じことになります。簡単な汚れのときは少しだけスプレーし、ひどい汚れのときはスプレーする回数をふやすのがコツです。この方法で汚れに合った洗剤濃度にすることができるわけです。プロは一見しただけで適正な洗剤濃度がわかりますが、一般の人はまず薄い濃度で使ってみて、汚れが落ちないようならスプレーする回数をふやしていくのがよいでしょう。この方法は、適正な洗剤濃度が得られるだけでなく、洗剤をむだ使いすることも防いでくれます。このように、洗剤ぶきをしたあとは、必ず水ぶきをして、洗剤分を残さないようにすれば完全です。
まず、洗剤ぶきです。これは汚れをとる方法として最も多く使われるものです。一般的には、洗剤をバケツの中にとかし、この中でぞうきんをしぼって使いますが、この方法では洗剤濃度が一定で、汚れぐあいに合わせることができません。それに、バケツの洗剤液がすぐに汚れてしまい、きたない水でふくことに抵抗を感じることもあります。かといって、何回もバケツの洗剤液を作り直していたのでは、不経済です。プロは、この方法をとらず、しぼったぬれぞうきんに洗剤をスプレーして使います。スプレーすることによって洗剤が均一に散り、バケツに洗剤をとかしたのと同じことになります。簡単な汚れのときは少しだけスプレーし、ひどい汚れのときはスプレーする回数をふやすのがコツです。この方法で汚れに合った洗剤濃度にすることができるわけです。プロは一見しただけで適正な洗剤濃度がわかりますが、一般の人はまず薄い濃度で使ってみて、汚れが落ちないようならスプレーする回数をふやしていくのがよいでしょう。この方法は、適正な洗剤濃度が得られるだけでなく、洗剤をむだ使いすることも防いでくれます。このように、洗剤ぶきをしたあとは、必ず水ぶきをして、洗剤分を残さないようにすれば完全です。
●洗剤がしみ込むといけない物は水ぶきで
次に、水ぶきです。水ぶきというのは、単に水でしぼったぞうきんでふくことです。洗剤ぶきのほうが汚れはよく落ちますが、見方を変えると、汚れをとると同時に物に洗剤の液をつけていることにもなります。水を吸い込む性質の物では、かえって洗剤が変色の原因になりかねません。
●水けをきらう物はからぶき
からぶきというのは、文字どおり、乾いたぞうきんでふくことです。この場合はふくというより、単にほこりを払う程度ですが、水けをきらう物の場合はからぶきがいちばん無難です。また、洗剤ぶきや水ぶきのあとのからぶきは、水けが残っているうちに行うこと。乾いたあとでは、汚れの水分がこびりつき、からぶきの意味が薄れます。ガラスふきの仕上げには、必ず完全に乾燥した布を使います。
●水ぶきとからぶきの中間、脱水ぶき
脱水ぶきというのは、脱水機で水けをきった生がわきのぞうきんでふく方法です。水けを残さずにふけることが利点です。 この方法は、からぶきのようにほこりをあたり一面に散らすこともなく、ふいたほこりをぞうきんにそっくり吸着させることができます。いわゆる化学ぞうきんはこの原理を利用したもので、水のかわりに石油系の油を薄くしみ込ませ、いつも生がわきの状態にしたものです。これをダストコントロール法といいます。
●こすってはいけない吸いとりぶき
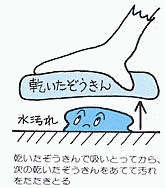 吸いとりぶきというのは、床などに何かをこぼしたときに、ぞうきんで吸いとる方法です。こすりとるのではなく、汚れの水分をぞうきんに吸いとらせて除去するやり方です。たとえば、じゅうたんの上にソースをこぼしてしまったときなど、ぞうきんでゴシゴシこすってしまうと汚れがどんどん広がり、中にまでしみ込んでしまいます。こんなときは、まず、乾いたぞうきんでそっと汚れの水分を吸いとらせます。こうして大半の水分を吸いとってしまったあと、乾いたぞうきんにたたき移します。この吸いとりぶきも、ぞうきんの大事な使い方の一つです。
吸いとりぶきというのは、床などに何かをこぼしたときに、ぞうきんで吸いとる方法です。こすりとるのではなく、汚れの水分をぞうきんに吸いとらせて除去するやり方です。たとえば、じゅうたんの上にソースをこぼしてしまったときなど、ぞうきんでゴシゴシこすってしまうと汚れがどんどん広がり、中にまでしみ込んでしまいます。こんなときは、まず、乾いたぞうきんでそっと汚れの水分を吸いとらせます。こうして大半の水分を吸いとってしまったあと、乾いたぞうきんにたたき移します。この吸いとりぶきも、ぞうきんの大事な使い方の一つです。
目次へ
プロ級「汚れ落とし」第二段楷は柄つきブラシ
●ぞうきんで落ちないときはブラシを使う
ぞうきんを使った掃除が第一段階だとすると、第二段階はブラシを使った方法です。洗剤ぶきでは汚れが落ちない場合に、この方法で試してみてください。ブラシの利点は、ぞうきんよりかたく、汚れをこすりとる力が強いことです。また、こまかいところの汚れをかき出せるという利点もあります。ブラシは、柄つきブラシとサッシブラシの二種類を用意するとよいでしょう。
●滑らずに使える柄つきブラシ
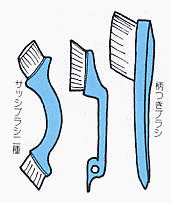 柄つきブラシは、その名のとおり、ブラシの端に持ち手のついたものです。この持ち手を握ることによって、ブラシにつけた洗剤が手につかず、滑らずに使いこなせます。力の入れ方も自在で、汚れに合わせた力でこすることもできます。この柄つきブラシを一本用意しておけば、たいていのクリーニングに使えて便利です。ただし、いくらぞうきんでは落ちなかったとはいえ、あまり強くこすらず、少しずつ力を入れてこするようにします。
柄つきブラシは、その名のとおり、ブラシの端に持ち手のついたものです。この持ち手を握ることによって、ブラシにつけた洗剤が手につかず、滑らずに使いこなせます。力の入れ方も自在で、汚れに合わせた力でこすることもできます。この柄つきブラシを一本用意しておけば、たいていのクリーニングに使えて便利です。ただし、いくらぞうきんでは落ちなかったとはいえ、あまり強くこすらず、少しずつ力を入れてこするようにします。
●アルミサッシのすみの汚れにはサッシブラシを
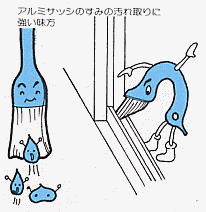 サッシブラシは、アルミサッシのすみの汚れをとるために作られたものですが、その他の場所でも使えます。現在では、ほとんどの家庭がアルミサッシを使っていますので、一本用意しておくとよいでしょう。サッシのすみの汚れをとりやすいように、毛足を長くし、腰が強く作られていることが特徴です。この毛足を利用して、すみにたまったほこりなどをかき出します。ちょっと変わった使い方としては、毛足の長さを利用して毛細管現象を起こし、これを利用するやり方があります。サッシブラシをぬらして軽く振り、水けをある程度払った状態でサッシのすみをこすります。すると、水の毛細管現象が起き、汚れがブラシの根元のほうへと吸い上げられていきます。アルミサッシのすみのほうは、こまかい汚れがなかなかとりにくいので、掃除の仕上げにこの方法を利用するとよいと思います。
サッシブラシは、アルミサッシのすみの汚れをとるために作られたものですが、その他の場所でも使えます。現在では、ほとんどの家庭がアルミサッシを使っていますので、一本用意しておくとよいでしょう。サッシのすみの汚れをとりやすいように、毛足を長くし、腰が強く作られていることが特徴です。この毛足を利用して、すみにたまったほこりなどをかき出します。ちょっと変わった使い方としては、毛足の長さを利用して毛細管現象を起こし、これを利用するやり方があります。サッシブラシをぬらして軽く振り、水けをある程度払った状態でサッシのすみをこすります。すると、水の毛細管現象が起き、汚れがブラシの根元のほうへと吸い上げられていきます。アルミサッシのすみのほうは、こまかい汚れがなかなかとりにくいので、掃除の仕上げにこの方法を利用するとよいと思います。
目次へ
プロ級「汚れ落とし」第三段階はスチールウールとサンドペーパーとヘラ
●最終段楷はスチールウール
ぞうきんやブラシでとれなかった汚れに対しては、第三段階としてスチールウールを使います。いわば、汚れ落としの最終段楷です。スチールウールは、鉄を細い糸状にして巻いたもので、家庭用品店やスーパーなどで簡単に手に入ります。金たわしと混同しがちですが、用途も強さも全く違います。このスチールウールは、汚れを削りとるものとしてはいちばん力が強く、それだけに物そのものにきずをつける可能性もあります。やみくもにこすらず、物の状態を見ながら注意深く使うことが肝心です。場合によっては、汚れが落ちなくとも、全体からみて物の風合いがそこなわれそうな場合は中止します。スチールウールでもとれない汚れは、もう限界としたほうがよいと思います。
●便器の水あかとりにはサンドペーパー
スチールウールと同じ程度の力を持っているのが耐水性サンドペーパーです。便器など、陶器製品についた水あかなどの汚れをとるために使います。目のあらさによっていろいろな番手があり、水あかとりには240番程度が使いやすいようです。これよりあらいペーパー(180番以下)ですと陶器にきずがつき、こまかいペーパー(320番以上)ですとこまかすぎて、汚れ落ちが悪く、汚れているところの周囲を先にきずつけてしまいます。
●こそげ落としたいときはヘラを使う
物の表面にたまってしまった汚れは、ヘラを使ってそぎ落としてから洗剤を使います。たとえば、換気扇についたひどい油汚れは、そのまま洗剤をかけても汚れを回しているだけで少しもきれいになりませんが、あらかじめヘラでそぎ落としておくと、洗剤の力を十分に発揮させることができます。汚れの種類や、物のかたさに応じて、金ベラ、プラスチックのヘラ、竹ベラ(割り箸でも可)などを使い分けます。
目次へ